鍵本 忠尚 氏プロフィール
株式会社ヘリオス / 代表取締役社長/医師
ハイクラス転職のクライス&カンパニー
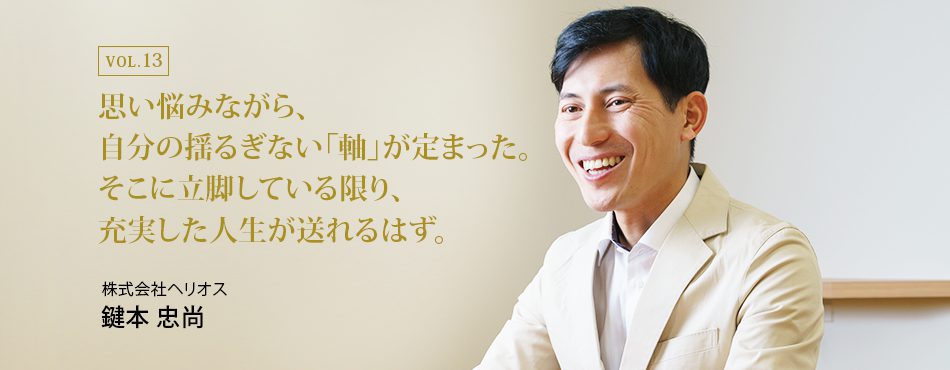
公開日:2016.02.22

株式会社ヘリオス / 代表取締役社長/医師
Interview
私は両親とも医師の家庭に育ちましたが、中学の時に「絵」に興味を持ち、キャンバスの上に絵の具を置くというシンプルな表現法に無限の可能性を感じて、高校時代までずっと油絵を描くことに没頭していました。 絵を描くというのは自分と向き合う作業であり、多感な年頃だったこともあって、自分の人生には何の意味があるのかという思いを巡らせながら、ひたすら絵を描いていましたね。高校2年までは、将来は画家になろうと真剣に考えていました。
高2の時、父親に「芸大に行きたい」と勢いのままに相談したら、「何を考えているんだ!」とひどく叱られて……自分自身、少し冷静になって考えてみると、別に「絵を描く」というのは習ってどうにかなるものでもありませんし、芸大に行ったからといって自分が描きたいものが得られるわけでもない。 もともと私にとって「絵を描く」ことは、自分という人間がどんな存在なのかを考えるような行為だったので、それで「人」について学びたいと考えるようになり、人を理解するための究極の学問である「医学」がやはり面白そうだと、そこから進路を180度転換し、九州大学の医学部に進みました。
お世辞にも真面目な学生とは言えませんでしたね。あまり授業にも出ていませんでしたし、でも興味のある領域だけはとことん追究していました。 特に面白かったのがウィルス学。ウィルスというのは、生物と非生物の境界にいるような存在で、遺伝子情報を有する最小単位なんですね。その境界を理解するとこで、我々の生命の仕組みを解明できないかというアプローチにとても惹かれたのです。 九大にはウィルス学で高名な教授がいらっしゃって、その先生の研究室に毎週足を運び、一緒に論文を読んでは議論していました。本当に優れた論文というのは芸術的で、仮説、実験、検証、結論までの流れが見事に構築されているんです。 その先生と過ごした時間は私にとって本当に貴重なものでしたが、振り返ると大学時代は、自分に何ができるのか、自分が何をすべきなのか、ずっと迷っていたように思います。
九大の医学部では6年次から博士課程がスタートするコースがあり、そこに入って1年間研究活動に取り組んだのですが、そこで日本の科学技術のレベルはきわめて高く、世界と伍して戦えるという手応えを感じました。 しかし、実際は日本発の医薬も治療法も欧米に比べて少ないのが現状で、国際学会でも日本人研究者の地位はけっして高くはなかった。日本人はやはり研究成果をアピールするのが下手なんですね。 このギャップを埋めるのが我々の世代の使命だと捉えたのですが、では何をすべきかと考えた時、そのひとつの手段がバイオベンチャーではないかと。当時日本はちょうど戦後50年を迎え、国力も充実し、ノーベル医学賞も利根川(進)先生が受賞されていて、世界を制するだけの蓄積はすでに十分にあると思っていました。 また、6年次にシリコンバレーに留学した際、アメリカでは大学の研究成果を実用化するバイオベンチャーという存在が当たり前になっており、日本にはまだそうした動きがあまり見られなかったこともあって、バイオベンチャーを立ち上げるのもひとつの選択肢だと考えるようになったのです。

シリコンバレーでの日々を経験して、いきなりバイオベンチャーを起業するのは無謀だと感じました。当時、アメリカの再生医療のパイオニアだった有名なベンチャーでさえも、資本主義の荒波に飲まれてリストラを重ねているような有様で、揺るぎない「軸」のようなものがないと、会社を立ち上げてもすぐに周囲に流されて倒れてしまうだろうと。 私の場合、その「軸」がまったく確立されていなかった。では、何を軸にすべきかと考えた時、当時私の本分はやはり医師であり、まずは臨床をやって患者さんを診ようと決意して、眼科医としてのキャリアをスタートしたのです。 そして患者さんに触れれば触れるほど、臨床だけでは自分の人生のミッションとして足りないと強く感じるようになって、自分たちの手で新しい治療法を生み出し、世界中の患者さんに届けたいと一社目のバイオベンチャーを立ち上げるに至ったのです。
ええ。自分がやるべきことを決断するにあたって、私は患者さんとの関わりのなかで3つの大きな出来事がありました。 1人目は、大学入学時の健康診断でがんが見つかった若い患者さん。すでに余命3カ月だったという悲しい経験。彼のことを思い出すたびに「人生はフェアじゃない」と痛感しますし、もし自分に時間があるのなら、それを有効に使わなければ彼に申し訳ないと強く思うようになりました。 その後、眼科医として勤務するようになってから、視神経炎を患って目が腫れてしまった患者さんを診ることになったのですが、あらゆる文献を読んでも腫れる原因がわからないというケースがありました。しかしステロイドを投与すると腫れが治まるので、原因がわからないまま退院いただいたのですが、1か月後、その方が入水自殺されたという報せが飛び込んできて…… ご家族の方によると「原因が不明なので、いつ失明するかわからないという恐怖に耐えられなくなった」とのこと。本当にショックでした。この2人目の経験から悟ったのは、人間には希望が必要だということです。
そうなんです。その患者さんとの一件があって、誰かが希望を創っていかなければならないのだとあらためて気づいたのです。 そして3人目の患者さんとの出会いが、私が起業する直接のきっかけになりました。 その時、加齢黄斑変性という、いま現在でも根本的な治療法のない、視力が失われてしまう病気を長らく患っていた方に出会ったのですが、その患者さんは、5年前に生まれたお孫さんの顔をまだご覧になっておらず、ぜひ一目見たいといつも望んでいらっしゃいました。 でもある日、その方がぼそっと「やっぱりこのまま死んでいくんですよね」とおっしゃられて、その言葉の重さに私は押しつぶされそうになりました。こうした患者さんに「まだ治療法はありません」と言い続ける人生は、私には耐えられない。 「必ずや有効な治療法を開発して多くの患者さんに届ける」と心に誓い、そして2005年に自らバイオベンチャーを興したのです。

不安がまったくなかったと言えば嘘になりますが、「新しい治療法を開発して患者さんに届ける」という自分の軸がぶれることがなければ大丈夫だろうと思っていました。 当時私はまだ20代後半でしたが、幸いにもスタートアップ時に20億円ほどの資金を調達することができ、九大で研究されていた技術を使った眼科手術補助剤の開発に挑むことに。世界のデファクトを取るためには、最大市場である米国から技術を発信するべきだと考え、すぐにアメリカに子会社を設立し、現地で開発チームを立ち上げて、当局と折衝して治験の最終試験である第III相試験に取り組みました。 日本のバイオベンチャーで、米国で単独で第III相試験を行った前例はなく、私たちが先駆け。結果、創業5年目で新薬の製品化に成功し、いまでは世界で12万人もの患者さんの治療に使われています。
実は大きな挫折も味わっています。開発した治験用新薬の生産をアメリカで企業に委託したのですが、そこで単純なミスが生じてしまい、一からすべてやり直さなければならない状況に陥りました。 ちょうどリーマン・ショック後で資金調達もままならず、リストラせざるを得ない事態に。 志を同じくして頑張ってくれていた研究者の仲間に会社から離れてもらわなければならなくなり、本当に心苦しくて辛い思いをしました。でも、心折れることなくその後も懸命に事業に取り組めたのは、「難病に苦しむ患者さんを治したい」という究極の目標があったからこそ。 そのためには苦しいことも自ら担わなければならないと、自分を奮い立たせていました。
ええ、私自身は本当に幸せな仕事に就いていると思っています。私がやるべきことは、多くの患者さんに治療法を届けること。 私が死ぬ時、果たして何人の患者さんを救えているだろうと、そのことだけを頭に描いて真っ直ぐに仕事に取り組めばいいわけですから。
すぐに「一緒にやりましょう!」と返事をしました。 大手の製薬会社であれば躊躇するような領域でしたが、私自身、臨床経験を持っていたこともあって「これはきっとよい治療法になる」という手応えを持っていました。何か新しいことにチャレンジする時、もちろんリスクは認識しますが、前例がないというだけで敬遠するのはあり得ない。 いま私たちの身の回りにある製品も、すべて前例のないところから誰かが創り上げてきたもの。医療の分野だって同じであり、そうしたチャレンジが人類の進歩につながっていくのだと思っています。
社名を変更し、上場も果たし、ようやくスタートラインに立ったという感じです。手元資金も拡充し、再生医療におけるパイプラインも揃い始めていますが、でもまだ全体の1~2%ほどしか進んでいません。 人類が治さなければならない病気はごまんとあり、長い勝負になりそうです。幸運にもiPS細胞による再生医療の分野は、日本が世界をリードしており、従来欧米企業がリードしてきた製薬業界の勢力地図を塗り替えられるチャンスです。 それをぜひモノにして、日本発で世界に大きな影響を及ぼす新産業の創出にも貢献していきたいと思っています。
ひとつ言えるのは、自分の人生を、過去を含めて肯定するしかないということです。 そのなかで何がしたいのか、徹底的に深掘りしてみるべきだと思います。私自身もいまの「軸」が定まるまでいろいろと悩みましたが、「軸」が見つかりさえすればあとは前に進むだけでした。 そこに迷いは起きないと思います。何のストレスもなく仕事に打ち込める。まさに充実した毎日です。自己否定ほど辛いものはありません。 いままでの自分をすべて肯定した上で、揺るぎ無い「軸」を見つけることで、チャレンジへの一歩が自然と踏み出せるのではないでしょうか。
構成:
山下和彦
撮影:
加藤昌人
※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

other interview post
インタビューを終えて