小沼 大地 氏プロフィール
NPO法人クロスフィールズ / 共同創業者・代表理事
ハイクラス転職のクライス&カンパニー

公開日:2018.06.06

NPO法人クロスフィールズ / 共同創業者・代表理事
Interview
最初に思い浮かぶのは小学生の時の転校ですね。私は小3で埼玉から横浜に引っ越したのですが、親から「横浜の子はみな勉強ができる」と脅されて(笑)、必死になって勉強したんです。でも実際はそこまでとんでもなく学力の高い地域だった訳ではなく、懸命に勉強した甲斐もあり、転校先の小学校で「デキる子」として周りから一目置かれるようになりました。調子に乗ってますます勉強に打ち込むようになって、中学受験をして神奈川県内の中高一貫の進学校に合格しました。でもそこで大きな挫折を味わってしまって……入学して最初のテストが酷い成績で、周囲にまったくついていけず、勉強が取り柄だった私のアイデンティティが崩壊してしまったんです。そんな痛烈な経験を味わい、自己防衛の意識が働いたのか、それから体育会系の部活に自分の価値を見出そうと熱中するようになったんです。
野球です。部活での私はとても熱かったのですが、でも肝心なところで自分に克てなかった。中3の時にキャプテンを任されたものの、一つ下の学年にとてもリーダーシップのある後輩がいて、彼のほうが絶対にうまくチームをまとめられるだろうという思いにずっと苛まれて、本当の意味での自信がもてなかった……そんな苦い思い出を払拭しようと、高校でも引き続き野球に打ち込みました。同じように3年の時にキャプテンを務め、絶対に勝つぞと頑張ってチームを率いたものの、また途中で息切れしてしまった。要はリーダーとしての資質が足りなかったんですね。もう辛くなって「この試合で負けたら重圧から解放される」と逃げの気持ちが湧いてしまい、リーダーがそんな体たらくなので、案の定、目標半ばにして敗退してしまいました。
ええ。敗北感を引き摺ったまま高校を卒業し、一橋大学に入学しましたが、「こんな人間で終わりたくない」ともう一度部活でリーダーシップを執りたいと決心したんです。これまでずっと部活に自分を投資してきて、何も残らないのでは虚しすぎる。この経験を糧に自分が成長した、と心から思いたい。できればレベルの高い環境で勝ちたいと、関東でもトップレベルの実力があって部員が100人以上もいる体育会ラクロス部に入部しました。そこでひたすら自分を追い込み、プレイヤーとしては3年生の時には21歳以下日本代表に選ばれ、4年生で主将に就任。特に4年生の時は、チームのために1年間を通じて一秒たりとも時間を無駄にしないという意識で生活を送りました。その1年間は本当にベストを尽くしたと堂々と言えますし、史上初の関東ベスト4という戦績を収めることができた。私自身も、最後まで踏ん張り切れなかった過去の情けない自分の亡霊と戦って、まさに悲願が成就した思いでした。
私は部活を通して、組織を率いるリーダーはどうあるべきなのかということを身体で学びましたし、その「どんな局面でも逃げずに向き合い続けるリーダーシップ」が、いま経営者としての自分の流儀になっています。
高校時代に読んだ社会学の本がきっかけでした。特に惹かれたのは文化相対主義という考え方。すべての文化は装置であり、何が正しいのか絶対的な答えはない。私が通っていた中学高校はカトリック系のミッションスクールで、隣人愛を教えられて育ったんですね。そして部活の顧問の先生に強く影響を受けたこともあり、私も将来、生徒たちに尽くして人格形成に寄与できる教師になりたいと思っていました。でも、その文化装置論に触れた時、隣人愛はあくまでキリスト教の価値観であって、世の中にはいろんな正義があるということに気づいたんです。そこにとても興味を抱いて、世の中には他にどんな装置があるのか知りたいと社会学部に進みました。
ええ。実は社会科の教員免許も持っています。あと、社会学部を選んだのはもうひとつ理由があって、私は天邪鬼なところがあるんですね。部活もそうで、高校では軟式野球、大学ではラクロスと、敢えてマイナーな世界に進み、そこで存在感を示すのが楽しかった。社会学も、メインストリームの法学や経済学に比べればマイナーな学問で、社会を複眼的に見るという、ちょっと捻くれた面が自分に合っていたようです(笑)。この学問で身につけた、物事に対して違う見方をするという姿勢は、いま事業をやる上でも活きていると思いますね。

先ほどお話ししたように、私は社会科の教師を志していたのですが、社会を知らずに先生になるのはどうかと思っていました。普通なら企業に就職して社会経験を積むのでしょうが、私は天邪鬼なので、そんなありきたりの選択は嫌だった(笑)。異文化への興味もあり、海外に飛び出して自分なりに社会を理解したいと思っていたところ、たまたま青年海外協力隊の広告を見て、JICAの募集説明会に参加したんです。そこで海外での活動を経験された方の話を聞き、自分の責任で自分の人生を生きている姿がとても格好良くて、直感的に参加を決断。そして、まだ紛争が起こる前のシリアに派遣されたのですが、そこでの経験が私の人生を変えました。
現地では、外資系コンサルファームのドイツ人コンサルタントがNPOのプロジェクトを支援していて、私はその人の直属の部下として働きました。そこで、ソーシャルの世界とビジネスの世界が融合すると面白い価値が生まれると実感したんです。コンサルタントのスキルを使うことで現地の活動の質が上がり、私が滞在していた村の生活が変わっていくのを目の当たりにして、これは凄いことだと。それまで私は、ビジネスというのはお金に汚い世界だと否定的に捉えていたのですが、決してそんなことはなく、むしろビジネスの力で社会を変えられる。また、社会貢献とビジネスを結びつけられる人材はまだまだ世の中では稀有だということも知り、では私がその役を担おう!と。それで、社会貢献の現場は経験したので今度はビジネスを学びたいと一緒に働いていたコンサルタントに相談したところ、マッキンゼーを勧められて、帰国後すぐに応募して入社することになりました。
シリアから戻ってコンサルタントになり、非常に濃密な3年間を過ごさせていただいたと思っています。ビジネスのイロハを徹底的に叩きこんでいただきました。またマッキンゼーは非常に忙しかったのですが、ビジネスをしながらも社会貢献に対する熱は押さえきれず(笑)、ソーシャルビジネスに関心を持つ仲間とともに勉強会を立ち上げたんです。彼らとの定期的なディスカッションは非常に刺激的で、自分の熱い気持ちを更に高め続けることが出来ました。クロスフィールズの共同創業者である松島(由佳氏)とも、そこでの活動を通じて想いを重ね合わせていったように思います。
ひとつは、先ほどお話しした青年海外協力隊の仕組みを企業向けにアレンジしたいという思いがあったのと、もうひとつはマッキンゼー在籍時に手がけた案件からの着想でした。ある小売業の組織変革に関わり、現場のエース社員を各店舗に短期で派遣して、彼らが触媒になって店舗運営のあり方を変えていくというスキームを実行し、大きな成果を上げたんですね。この2つを結びつけて「留職」のビジネスプランを立てました。
はい、議論は大いにあり、迷った上でNPO法人を選択しました。いくつか理由はありますが、一番大きいのは、自分たちがNPO法人として大きく成長していくことで、世間からのNPOへの見方を変えていきたいという強い想いです。21世紀の日本を考えると、社会の課題は急速に複雑化・多様化していて、もはや行政や企業だけでは解決できない状態になってきている。そんな時代背景のなかでNPOが果たす役割はこれからの社会で急速に大きくなるという確信がありましたし、まだまだ発展途上の日本のNPOの業界の発展を自分たちで牽引していきたいと、そう松島とも話して決めました。
もうずっと大変なのですが(笑)、3年目ぐらいに自分にとって非常に辛い時期がありました。私のリーダーとしての持ち味は「明るさ」と「前向きさ」だと思っているのですが、当時もミーティングではいつも明るく振る舞い、メンバーから課題を持ちかけられると、常に前向きに捉えて「必ず解決できるよ!」と鼓舞していました。でもそのうちメンバーたちから、その明るさと前向きさが敬遠されるようになって……何か相談しても、すべて前向きに歪めて明るく返されるのがイヤだと。
本当にショックでした。私は知らず知らずのうちに、そうした場でメンバーの感情を抑え込んでしまっていたんです。でも感情が解放されないと、やはり人は疲弊する。当時の私は、目の前の課題にフォーカスして戦略を考えることばかりに意識が向いていて、気がつけばメンバーたちの心が澱んで組織が崩れかけていたんです。
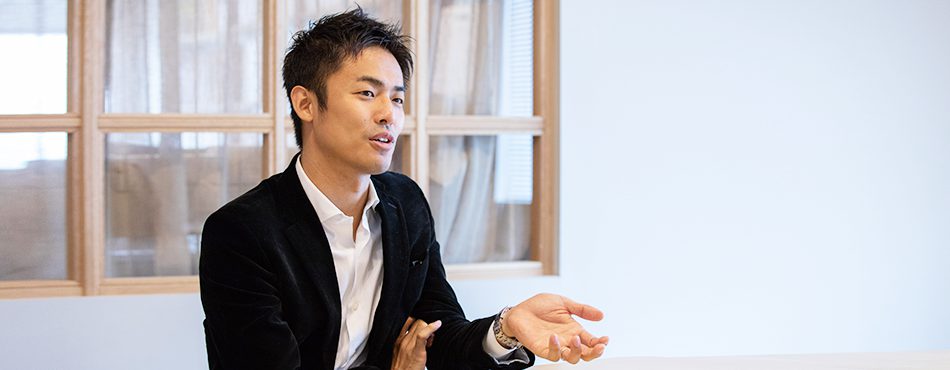
何とかしなければと、チームの合宿で膿を出すコミュニケーションを図りました。でもそこでメンバーたちがみな息苦しそうな様子に触れて、もう「どうしていいかわからない」とみんなの前で泣きながら弱音を吐いてしまって……でも、メンバーたちは「その言葉が聞きたかった」と。学生時代の部活は、ある種のマッチョイズムで、自分が完璧になり、それをみんなにも要求してチームを引っ張れた。ある意味、同質性の高い集団での短距離走型のリーダーシップだったんです。でもNPOは、ここに関わるみんなが、それぞれ人生を捧げて長期的にコミットしている。こうした組織を引っ張るためには、ポジティブなこともネガティブなことも、すべて受け入れるコミュニケーションが必要だったんです。それを機に自分のなかでリーダーシップのあり方が変わりました。まあ10年以上に渡って培ってきた、自分のリーダーとしてのプロトコルをすべて壊すことになるわけですから、正直、受け入れるのには時間はかかりました。でも、我々は『すべての人が、「働くこと」を通じて、想い・情熱を実現することのできる世界』を目指すことをビジョンに掲げているのに、私自身がそれを実践できていないなんて、こんな自己矛盾はない。だから絶対に自分を変えなければと。
いまひとつの山を登頂し、また次の山を登ろうとしている感じですね。20代後半の頃、「留職」という得体の知れないビジネスモデルを考え、「この価値を世の中で証明したい!」というのが起業時の私の夢でした。いまの自分から見れば小さな夢ですが、でも当時の私には垂直にそびえる壁のようで、それを仲間たちとともに必死で登って成果を出し、社会に一定のインパクトを与えることができた。でも、その山を登り切ったいま、また違う景色が見えてきて、自分たちの山登りの技術も磨かれて装備も増えてきたので、次に制覇する山を見つけて登り始めたところです。
いまや人生100年時代ですから、一直線でキャリアを考えるのではなく、人生のなかで何回かピボットしながら、チャレンジしたいことを楽しむのもいいんじゃないかと思いますね。同世代のNPO業界の起業家と話をしていると、良くも悪くもミッションに忠実な人が多いんです。私もかつてはそうだったのですが、若い頃の原体験からくる「ミッション原理主義者」は、危険な面もある。時代は常に動いています。ミッションに立ち返ることは大切だと思いますが、あまりにそこに縛られ過ぎると飛躍しないし、無理も生じてくる。
実は2年前から取り組んでいるテーマがあり、それを事業化して「留職」とともに新たな柱にして行く方針です。私は変革を続けていくNPOの経営者として、絶えず方向性を変えて新しいステージに挑んでいきたいと思っています。
最近、私が心に留めているのは、自分を「一人称」でみるということです。先日、きっかけがあって黒澤明監督の映画「生きる」を初めて見たんですね。主人公はしがない公務員で、彼はがんを宣告されて自棄になってしまうものの、残された人生に自分の生きる意味を見つけようと、住民から陳情のあった公園の建設に奔走するんです。さまざまなしがらみを突破して立派な公園を完成させるのですが、その手柄は役所の重役に横取りされ、彼の功績は日の目を見るに至らなかった。結局彼はその公園のブランコに乗っている時に絶命してしまうんですね。さぞ失意の中で亡くなったのだろうと思っていたら、実はその直前、彼は鼻歌を歌いながらブランコに乗り、公園で遊ぶ子供たちを嬉しそうに眺めていたことが判明して……別に誰かに称賛されなくとも、この公園を造り上げたことで、彼としては本当に幸せで満足のいく人生を終えることが出来たんだと。そのシーンに私はもの凄く感動して、あらためて自分を省みてみました。私は「周りの人に影響を与えたい」という想いを軸に生きてきて、葬式のときに何人の人が私に影響を受けたと思ってくれるかなんてことを人生の目標に置いてきた節がありました。それで自分の人生本当に良いのか、と。結局、自分の人生が幸せかどうかは、自分が決めることであり、自分しか感じられないことなんだと思うんです。他人からどう思われるかではなく、自分がどう思うかということ。ですから何かチャレンジしたいことがある方も、いま動きたくないのなら動かなくていいと思いますし、周囲から動いてほしいと言われて動くのも筋が違うと思います。「一人称」で考え、自分はどうなのかと。人生が終わる瞬間に自分で自分の人生をどう思えるか、それを基準に行動を決めていくほうがきっと幸せなのではないか。私はそう考えています。
構成:
山下和彦
撮影:
櫻井健司
※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

other interview post
インタビューを終えて